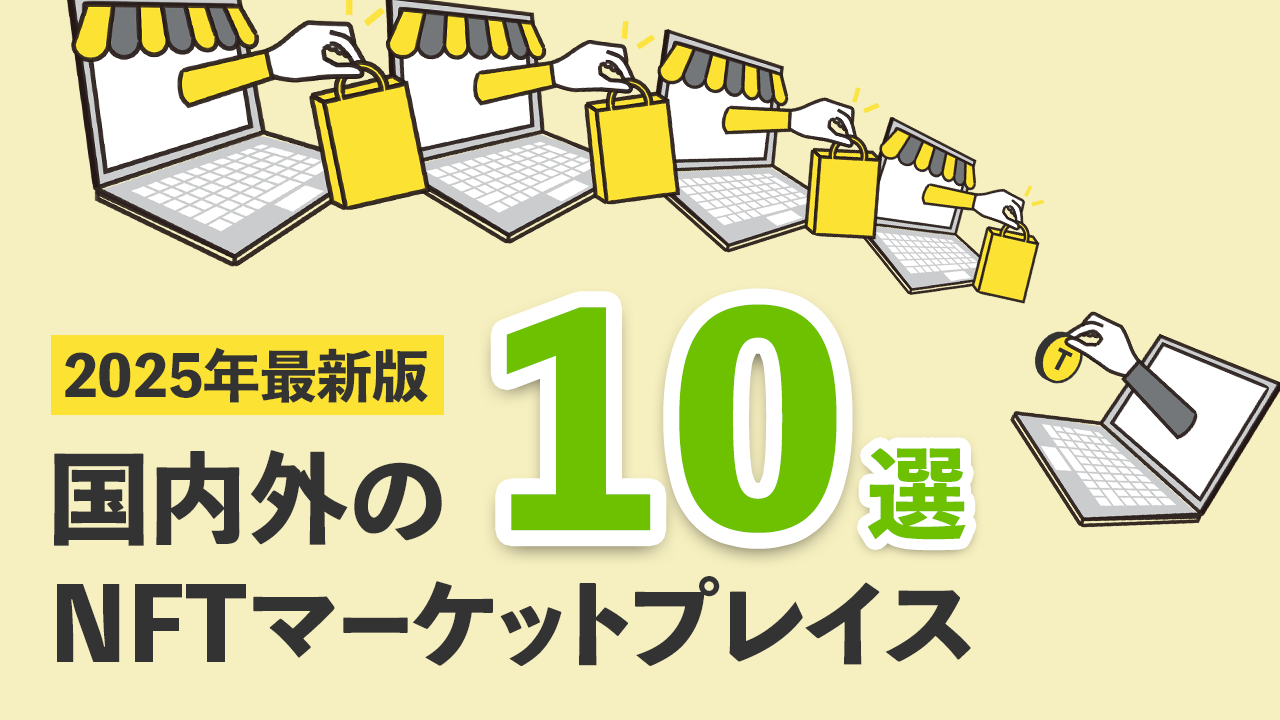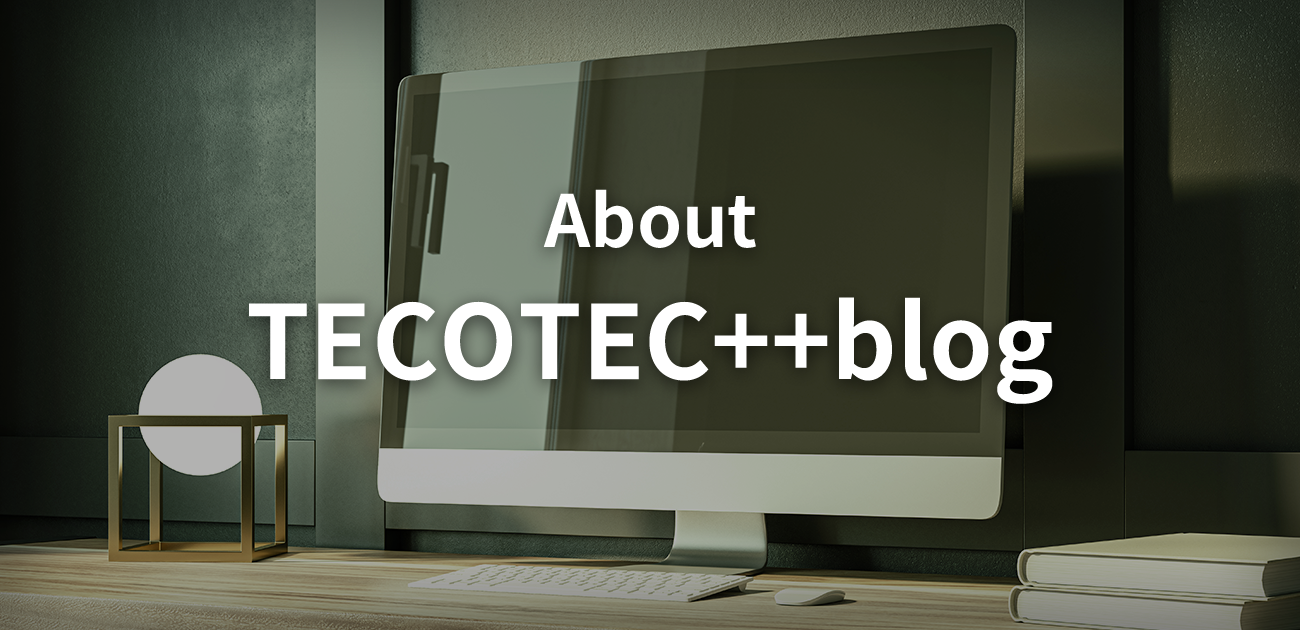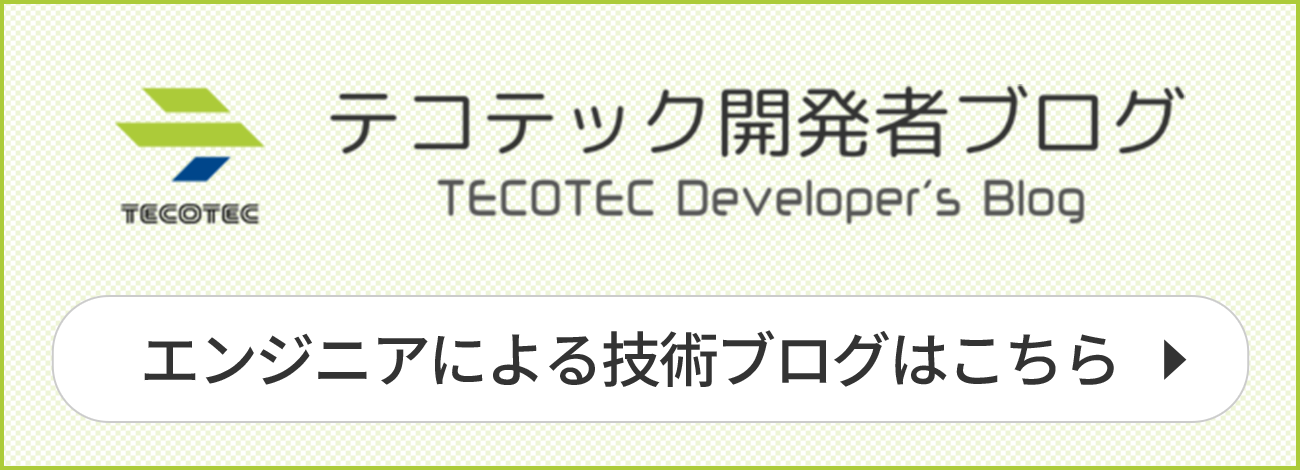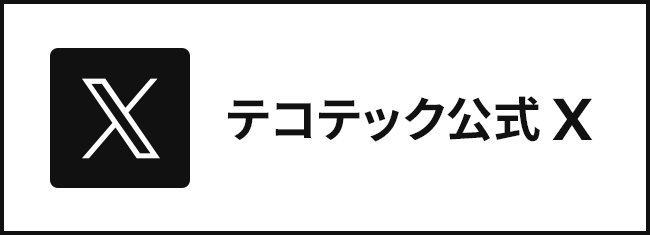テコテック++ブログTOP
テコテック++ブログTOP
【生成AI徹底比較】「ChatGPT」と「Gemini」の違いを分かりやすく解説

急速に普及し始め、様々な生成AIサービスが登場
近年、AI技術は急速な進化を遂げており、ビジネスシーンのみならず個人でも手軽にAIを活用する時代が到来しています。AIの普及に伴い、様々な企業やユーザーがAI導入を検討する中で多くの人が直面するのは、「どちらのサービスが自分に合う生成AIなの?」「こっちのサービスとあっちのサービスで何が違うの?」という問題です。
本記事では、生成AI初心者の方に向けて、世の中に溢れる生成AIサービスの中から代表的なサービスをピックアップし、それぞれの特徴やどのような方に向いているのかなどを比較、解説し、ビジネスシーンや個人利用において最適な生成AIサービスを選択する上で、役立つ情報をお届けします。
対話型AIサービス「ChatGPT」と「Gemini」を比較

今回は、生成AIブームの火付け役と言っても過言ではないOpenAIが開発した「ChatGPT」と、Google DeepMindがGoogle AIを活用して開発した「Gemini」を比較してご紹介します。
まずは「ChatGPT」と「Gemini」それぞれの基本情報を知ることから始めたいと思うのですが、せっかくなので「ChatGPT」と「Gemini」双方に“自己紹介”という形でサービスの紹介をしてもらいましょう。
「ChatGPT」とは
「ChatGPT」は、OpenAIが開発した会話型AIツールで、文章生成や質問応答、プログラミング支援など、幅広い用途で活用されています。このツールは、ユーザーの入力に応じて自然な文章を生成する能力を持ち、個人利用からビジネスまで多様なニーズに対応します。特に、簡単な操作性と直感的なインターフェースが特徴です。
<「ChatGPT」の生成文章を抜粋>
「ChatGPT」は無料プランと有料プラン(ChatGPT Plus)を提供しており、有料プランでは高度な機能を持つGPT-4が利用可能です。Microsoft製品(OfficeやAzure)とも統合されており、企業での利用が広がっています。
「Gemini」とは
「Gemini」は、Google AIが開発した大規模言語モデルです。「ChatGPT」と同様に、文章生成、質問応答、翻訳など、幅広いタスクをこなせるAIモデルとして注目されています。「Gemini」は、その高度な言語理解能力と生成能力により、より自然で人間らしい対話を実現することを目指しています。
<「Gemini」の生成文章を抜粋>
「Gemini」の最大の特徴は、その多様な能力にあります。文章の作成はもちろん、コードの生成、異なる言語間の翻訳、そして複雑な質問への回答など、様々なタスクを高い精度で行うことができます。また、「Gemini」は、文脈を深く理解し、それに基づいた応答を生成することができるため、より自然で人間らしい対話が可能です。
「Gemini」は、Googleの様々な製品やサービスと連携することで、より幅広いユーザーに利用されることが期待されています。例えば、Google検索との連携により、より高度な検索体験を提供や、Google Workspaceとの連携により、生産性を向上させるツールとして活用されることが考えられます。
「Gemini」は、まだ開発段階にあるモデルですが、その高い性能と多様な可能性から、今後のAIの発展を大きく牽引する存在となることが期待されています。
それぞれのサービスに“自己紹介”をしてもらいましたが、この時点で双方の個性がうかがえると思います。
「ChatGPT」と「Gemini」の特徴

先に記載した“自己紹介”でお分かりのように、同じAIでも開発会社が違うことで独自性が生まれるため、それぞれの特徴を把握しておくことが生成AIを選ぶ基準として重要になります。それぞれのサービスの主な特徴を確認していきます。
「ChatGPT」の特徴
・汎用性の高さ
文章生成でレポートやメールの自動作成、ブログ記事の執筆支援や、お客さまからの問い合わせ対応、コードの作成、修正、最適化などのプログラミング支援まで幅広く利用可能です。
・ユーザー指示への柔軟な対応
プロンプト(入力内容)に応じて出力される答えをカスタマイズできるため、わからないことをAIに質問して基礎知識を学ぶことや、専門家が具体的な問題解決策を得る場合などに活用できます。
・直感的な操作性
初心者でも簡単に使いこなせる直感的なインターフェースで、プラグインや外部ツールとの連携も充実しており、業務フローに組み込みやすい特徴があります。
・価格設定
無料プランで基本的な機能は試すことができ、有料プラン(ChatGPT Plus)では、高度な機能を持つGPT-4を利用することが可能で、ビジネスシーンでの利用に適しています。
「Gemini」の特徴
・マルチモーダル能力
「マルチモーダル」とは、テキストだけでなく画像・動画・音声・コードといった複数種類のデータを一度に処理できるAI技術で、「Gemini」は、商品画像から自動でタグ付けや紹介文を生成する画像認識や、ソースコードのセキュリティ検証やバグ修正などのコード分析などの処理が可能です。
・Googleサービスとの統合
既存のGoogleサービスとの連携で業務効率を向上することができます。例えば、GmailやGoogle Docsとの直接連携が可能で、日常業務の効率を大幅に向上させます。またGoogle検索を活用した精度の高い情報取得も可能です。
・データの広さと質
Googleの膨大なデータセットを基盤とした情報を提供することができます。最新情報を素早く取得し、特にSEO対策やマーケティング分野で優れたパフォーマンスを発揮します。
・スケーラビリティ(拡張性や拡張可能性)
個人から企業の大規模プロジェクトまで柔軟に対応が可能です。特にクラウド環境を利用する企業にとって、スケーラブルな活用が期待できます。
■ChatGPTとGeminiの比較表
| 項目 | ChatGPT | Gemini |
|---|---|---|
| 開発企業 | OpenAI | Google DeepMind |
| 主な用途 | 会話型AI、文章生成、プログラミング支援 | 検索、会話型AI、画像・コード処理 |
| 技術的特徴 | GPT-4ベース、文脈理解に優れる | マルチモーダル対応、Google検索との統合 |
| マルチモーダル対応 | 画像、テキスト、音声の処理(GPT-4の一部で対応) | 画像、テキスト、音声、動画、コードを統合処理 |
| トレーニングデータ | 公開データセット+独自データ | Googleエコシステムの膨大なデータ |
| ユーザー体験 | シンプルで直感的、幅広いプラットフォーム | Googleサービスと深く統合 |
| 価格設定 | 無料プラン+有料プラン(API利用料あり) | 無料プラン+有料プラン(商業利用プラン) |
| 将来性 | Microsoftとの提携、Office統合 | Google検索市場の強みを活用 |
「ChatGPT」は、自然な対話を得意としており、お客さま対応や文章作成など、幅広い用途に活用できます。一方、「Gemini」は、画像認識やコード処理、Googleサービスとの連携などの拡張性の高さが特徴です。自然な対話やクリエイティブな文章作成を求める場合は「ChatGPT」、多様なデータ処理や最新情報が必要な場合は「Gemini」という使い分けができそうです。
自分に合った生成AIの選び方

それぞれサービスの特徴を深堀することができたところで、ここからが本題です。冒頭に述べた「どっちが自分に合う生成AIなのか」について、活用例を交えて紹介していきます。
「ChatGPT」が向いている企業やユーザー
1. 中小企業や個人事業主
作業コストを抑えて効率的に活用できるため、中小企業や個人事業主に最適です。限られた人員でも業務を効率化し、生産性を向上させることができます。
<活用例>
・事務作業の自動化
打ち合わせの議事録作成や、売上データ・顧客情報の整理をフォーマットに沿って自動化し、スプレッドシートへの入力作業を効率化して事務作業の負担を軽減します。
2. クリエイティブ業務が中心のユーザー
ライティングやアイデア出しに強みを発揮するため、クリエイティブな業務に関わるユーザーに向いています。クリエイターは発想の幅を広げながら、作業効率が向上します。
<活用例>
・ライターや編集者のコンテンツ作成
ブログ記事、SNS投稿、ニュースレターなどの記事構成の提案や原稿の校正に利用します。特に大量の文章作成が必要なプロジェクトで時間を短縮することが可能です。
3. プログラミングを支援したいユーザー
プログラムのコード作成や修正や、ソフトウェア開発や技術的な質問に対応できるため、IT企業やフリーランスで働くエンジニアのサポート役として活躍します。
<活用例>
・開発チームの生産性向上
簡単なスクリプトやプログラムのサンプルコードを生成し、開発効率を向上させます。冗長な処理を削減し、より効率的なコードへ改善するアドバイスをもらい対応していきます。
「Gemini」が向いている企業やユーザー
1. Googleツールを利用している企業
Google Workspaceとの統合性が高いため、Googleツールを多く活用している企業には導入ハードルも低く、効果的に利用できます。
<活用例>
・営業チーム
Gmailを通じて顧客データを効率的に管理し、会話履歴から次のアクションを提案できます。Google Docsを活用したドキュメント作成も可能で、報告書やプレゼン資料を迅速に作成できます。
2. 大規模なデータ分析を必要とする企業
Googleの検索技術とAI能力を活用できるため、マーケティングやリサーチなどデータ分析が必要なマーケティング会社や広告業界の業務効率化が期待できます。
<活用例>
・マーケティング・広告業界
Google検索データを活用した最新のトレンド分析を行うことで、広告のターゲット層に応じたキャッチコピーや広告文の作成や競合分析が行えます。
3. 複合情報処理を扱うユーザー
文字、画像、音声、動画など、複数の異なる種類の情報を扱う、クリエイティブ分野や技術分野に携わるユーザーの作業効率を向上させます。
<活用例>
・教育関連の学習支援企業
画像やテキスト、音声を組み合わせたインタラクティブな教材の作成が可能です。手書きのノートや図をデジタル化し、要点を自動で抽出した最適なドキュメントの作成にも役立ちます。
生成AIの利用における注意点とリスク

「ChatGPT」と「Gemini」はどちらも非常に便利なツールとして活用できますが、誤った使い方をしてしまうと、思わぬトラブルに繋がる可能性があります。生成AIを活用する際の注意すべきポイントやリスクについて、起こりうるケースを交えて紹介します。
1. 情報の正確性
生成AIが提供する情報は、必ずしも正確または最新であるとは限りません。特に専門性が求められる分野では、誤った情報が含まれる可能性があります。
ケース①:生成AIを利用して契約書のテンプレートを作成した際、一部の法的表現が誤解を招く形で生成され、契約トラブルにつながった。
ケース②:広告マーケティングのターゲティングを行う際、生成AIが提供する検索結果の要約が古い情報に基づいていたため、ターゲット層を誤って設定してしまった。
2. プライバシーとセキュリティ
生成AIに入力した情報がAIのトレーニングや分析に利用される可能性があります。特に機密情報や個人情報を扱う際には注意が必要です。
ケース①:生成AIを利用して内部メモを作成したが、機密事項を含む内容を入力してしまった。後に入力した情報が外部で利用されるリスクを懸念し、企業が生成AIの利用を禁止した。
ケース②:社内プロジェクトの資料を生成AIを利用して自動生成した際、外部に保存されたデータが漏洩するリスクが指摘された。
3. バイアスのリスク
生成AIは、学習に用いたデータセットに依存するため、特定の視点や偏見を含む回答を生成する可能性があります。
ケース①:生成AIがマーケティングキャンペーン向けのキャッチコピーを生成した際、性別や文化に対する不適切な表現が含まれてしまった。
ケース②:画像生成AI機能を活用して商品プロモーションを行ったが、人種や性別の多様性を欠いたイラストを提案してしまい、不適切であるとクレームに繋がった。
4. 依存のリスク
AIツールに過度に依存すると、人間の判断力や創造性が低下する可能性があります。これにより、プロジェクトの質や独自性が損なわれるリスクが懸念されます。
ケース①:教育現場で生成AIを利用した課題解決を推奨した結果、学生が独自の考察を行わなくなり、学習の深度が浅くなる傾向が見られた。
ケース②:生成AIを使って市場分析を完全に自動化したが、分析内容の一部に誤りが含まれていたことに気づかず、新商品のターゲット設定に失敗してしまった。
上記の注意点とリスクに加えて、生成AIツールを利用する際には、各サービスの利用規約やプライバシーポリシーを十分に確認し、それに準じた適切な利用を心がけることが重要です。特に、データの取り扱いや禁止事項については、各サービスによって異なるため、利用前に必ず最新の規約を確認してください。
生成AIの効果的な活用のためのポイント

「ChatGPT」や「Gemini」をより効果的に活用するためには、以下のリスクや注意点を認識し、適切な運用ルールを整えることが必要です。
1. 情報確認のプロセスを設ける
生成された内容を専門家や信頼できるリソースで確認する。
2. 入力内容の管理
機密情報や個人情報を入力しない運用ルールを策定する。
3. バイアス検証を行う
出力内容を多角的な視点で評価し、公平性を確保する。
4. 適度な活用を意識する
AIを補助ツールとして使い、最終判断は人間が行うようにする。
まとめ
「ChatGPT」と「Gemini」は、それぞれ独自の特徴と強みを持つ生成AIツールであり、目的やニーズに応じた活用が求められます。
「ChatGPT」は汎用性が高く、幅広いユーザーに対応する柔軟なツールとして、中小企業や個人事業主、クリエイティブな業務を担う方に最適です。「Gemini」はGoogleエコシステムとの統合やマルチモーダル能力を活かし、特にデータ分析やGoogleツールを活用する企業に向いています。目的に合わせてうまく使い分けることができれば、より良い成果を得られる可能性もあります。
ただし、どちらのツールを選ぶ場合でも、情報の正確性、プライバシーとセキュリティ、バイアスのリスクなどに注意し、AIの結果を盲信することなく適切に活用することが重要です。これらを踏まえたうえで、それぞれのツールが提供する可能性を最大限に引き出すことで、業務の効率化や創造性の向上につながるでしょう。
生成AIは今後も進化を続け、私たちの生活やビジネスにおいてさらに重要な役割を果たしていくことが予想されます。新たな可能性を見出し、競争力を高める一助として生成AIを役立ててみてはいかがでしょうか。
筆者:TECOTEC++blog編集部